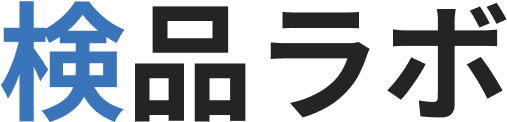私たちの手元に届く製品が「当たり前にきれい」である背景には、誰かの細やかな確認作業が存在します。
このコラムでは、普段あまり表に出ることのない「検品」という仕事にスポットを当て、その役割、実際の現場、そして今後の展望について掘り下げてみたいと思います。
検品が担う、品質保証の“最終工程”とは
製造から納品までの流れにおいて、検品は最終チェックの役割を果たします。
ここで不良品を見逃してしまえば、クレームやブランドイメージの損失といった、目に見えないコストが発生します。
特にアパレルや雑貨では、「見た目の印象」が品質評価に直結するため、汚れや縫製不良、異物混入など、些細なミスも見逃せません。
検品の現場では、「ルールを守る」だけでなく、「気づく力」や「違和感を察知する感覚」も非常に重要とされています。
人の目 VS 機械検品、これからの品質管理はどう変わる?
近年、AIや画像認識による検品システムの導入が進んでいます。
一定のパターンに基づく異常検知や高速な処理においては、機械が人の作業を補完・代替する時代に入っています。
しかし、たとえば「色の違和感」「形状の微妙なズレ」「感触の違い」といった“直感的な不良”の多くは、依然として人の目と感覚に頼らざるを得ません。
機械化が進んでも、人と機械のハイブリッドで品質を守る時代がしばらくは続きそうです。
実際に検品業務に携わるスタッフに話を聞くと、「自分の目が最後の砦になる責任感がある」「クレームを未然に防げた時の達成感は大きい」と語る人が多くいます。
また、「初めは気づけなかった不良も、経験を積むごとに見えるようになった」といった声も多く、検品はまさに“職人的な感覚”が求められる仕事です。
効率やスピードが重視される時代だからこそ、「目に見えない価値」を丁寧に扱う現場の仕事が、あらためて見直されています。